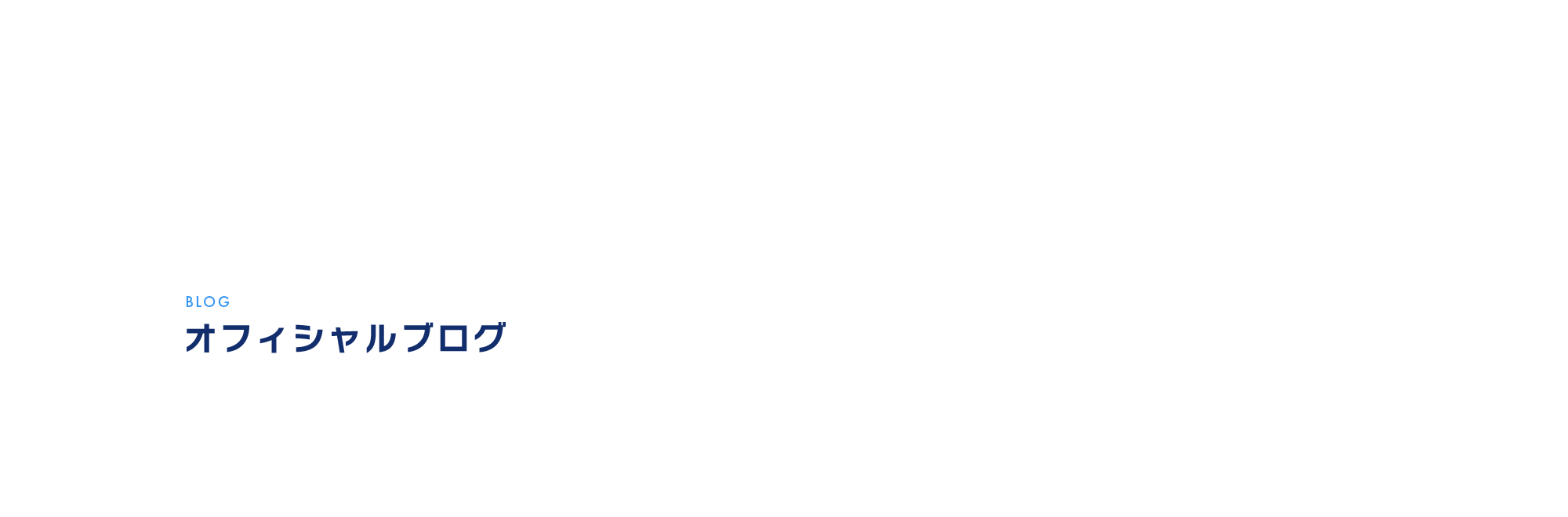清掃業は現場力×仕組みの産業。人手不足・単価圧力・クレームリスクの三重苦を越えるには、標準化とデジタルが決め手です。ここではビルメン・店舗・宿泊・製造現場を対象に、経営と現場の両輪を解説します。
目次
1|品質は“色と順路”で作る——クロス色分け&動線設計 ️
-
色分け:赤=トイレ、青=ガラス、黄=什器、緑=キッチン等。交差汚染ゼロが基本。
-
一筆書き動線:高所→什器→床。乾式→湿式の順でリワーク削減。
-
チェックリスト:“触る順”で並ぶ表に。写真付きで新人が初日から戦力に。
2|SDS・希釈・保管——“薬品の三種の神器”
-
**SDS(安全データシート)**は現場ファイル化、緊急連絡先とセット掲示。
-
ディスペンサーで希釈固定→ムラ・コスト・素材ダメージを防止。
-
ロッカー管理:酸・アルカリ・塩素は分けて保管、温度直射日光NG。
3|安全は最優先——転倒・落下・化学物質
-
スリップ対策:濡れ床サイン+ゾーニング、作業は端から出口へ後退。
-
高所:脚立3点支持・親綱、2人一組。
-
化学:混用禁止教育を入社・月次で反復。手袋・ゴーグル・マスクを常備。
4|DXで“迷わせない・待たせない” ️
-
スケジュールアプリ:現場ごとに手順・写真・図面を紐付け。
-
実績はQR打刻→在室証跡と作業時間を自動集計。
-
品質監査:チェック結果をダッシュボードで可視化、再発防止のPDCAへ。
5|KPIと原価の見える化
-
定期:完了率/再清掃率/標準工数差
-
日常:作業残/緊急呼び出し件数/応答時間
-
原価:人件費%・薬剤費%・移動時間・教育時間
→ 週1の15分スタンドアップで“数字→原因→対策→担当→期限”。
6|現場教育:90日オンボーディング
-
Day1–7:安全・道具・色分け・動線。“触って覚える”実地3時間/日
-
Day8–30:小面積の担当現場→1枚写真報告の習慣化
-
Day31–60:夜間現場・高所・剥離洗浄の基礎
-
Day61–90:単独巡回+不具合報告→是正までを完走
7|剥離・洗浄・コーティングの勝ちパターン
-
剥離:区画を小さく、濃度は規定内。湿潤保持→吸水→リンスを丁寧に。
-
石材:酸NGの識別徹底。ダイヤ研磨→含浸で長期の艶に。
-
カーペット:ドライ→パイル起こし→前処理→洗浄→リンス→速乾。送風・除湿で再汚染抑制。
8|エコ清掃と省エネ
-
低VOC・中性主体へ移行、超純水清掃で薬剤レスな箇所を拡大。
-
バッテリー機器で夜間騒音↓、電力ピークも回避。
-
ごみ分別の写真サインで回収品質を安定。
9|価格設計と提案力
-
時間単価×標準工数×頻度を軸に、**“成果基準(品質レベル)”**で合意。
-
初回現調→写真と面積表→ゾーニング単価で透明化。
-
ミニ改善を月次提案(マット位置変更・サイン追加・動線見直し)で解約率↓。
10|採用と定着:人が辞めない組織の作り方
-
固定現場+希望シフト、15分早退可など柔軟性。
-
評価は“できた行動”(色分け厳守・事故ゼロ・顧客褒め)で見える賃金へ。
-
1on1を月1(10分)→感謝と改善1つを言語化。紹介制度で採用コスト↓。
11|ケース:24hジムの日常清掃を刷新 ️♀️
-
課題:汗汚れの臭い/夜間クレーム/鏡ムラ
-
施策:色分け徹底、超純水+スクイジーで鏡筋ゼロ、黙清掃サインで苦情減
-
結果:アンケート★+0.6、早朝会員の継続率↑、再清掃依頼▲70%。
12|“30日で変える”改善ロードマップ ️⚙️
-
Day1–7:色分け・動線図・SDS掲示を統一
-
Day8–14:希釈器導入/QR打刻開始
-
Day15–21:品質監査のテンプレ運用→ダッシュボード公開
-
Day22–30:定例ミーティング(15分)と月次ミニ改善の提出を定着
まとめ ✨
清掃業の競争力は、安全に“同じ良さ”を繰り返せる仕組みで決まります。
色分け×動線×希釈×DX——この4点セットで、**品質↑・事故↓・原価↓・離職↓**を同時に実現。
「現場で昨日より良くする」小さな一歩を、今日から始めましょう。